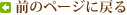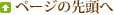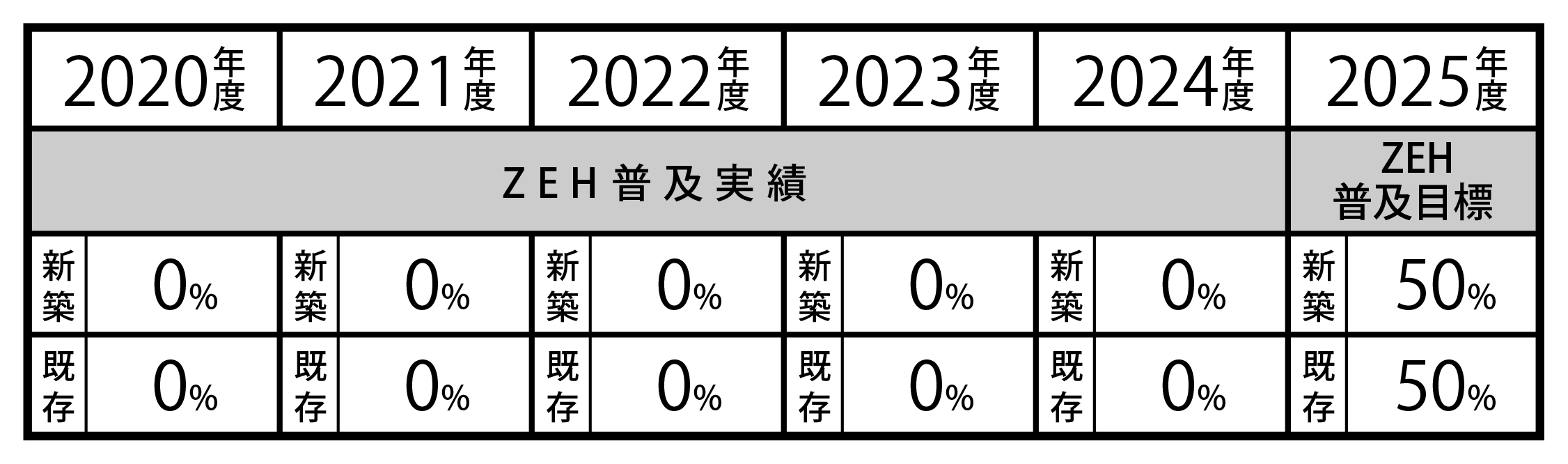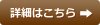2024年03月14日
こんにちは ( ^ω^ )
エルデザイン広報のながちゃんです。

近年、薄毛で悩む若年層が増加傾向にあると言われています。
20〜30代で、薄毛の悩みを抱える若い男性が多いそうです。
●薄毛は何人に1人ですか?
年代別の薄毛の割合は20代が約10%、30代が約20%、40代は約30%、
50代以降では約40%であるとの統計があります。
年齢が高くなるにつれ薄毛の割合は高くなり、
全年齢の平均から見ると 3人に1人が薄毛だと言われているのです。
●日本人男性が薄毛を気にしはじめる年齢:38歳
女性が薄毛を気にしはじめる年齢:42歳
●将来薄毛になりやすい人の特徴
家族に薄毛の人がいる。
生活習慣が乱れている。
ストレスを感じやすい。
誤ったヘアケアをしている。
薄毛に関する遺伝子は、高い確率で子や孫に引き継がれることがわかっています。
確率としては70〜95%と非常に高い数字なので、
家族に薄毛の人がいる方はそうでない人に比べて薄毛リスクが高いといえるでしょう。
遺伝以外では、生活習慣やストレス、ヘアケア方法なども薄毛の原因になると考えられています。
見た目的な特徴としては、抜け毛の増加や生え際の後退、
頭頂部(つむじ)が透けて見えるといった症状も薄毛が進行する前兆です。
皆さんは、どうでしたか?
●それも魅力! 「ハゲててもかっこいい有名人」
【1位】渡辺謙(28.9%)
【2位】ブルース・ウィリス(19.9%)
【3位】竹中直人(11.5%)
気にするのも良いですが、
薄くても隠さず堂々としているほうがカッコイイように思えます。
エルデザイン広報担当
ながちゃんでした ( ^ω^ )